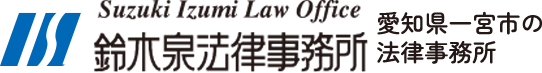取扱分野
交通事故
交通事故に遭うと、加害者側の保険会社から示談額を提示されます。弁護士にご依頼いただくと、代理人として保険会社と交渉をして、裁判基準(弁護士基準)による賠償額を目指すことが可能になります。後遺症が残った場合には、適正な後遺障害等級認定を得られるよう、尽力いたします。
対応内容
自賠責請求、任意保険会社との交渉、裁判基準(弁護士基準)での損害賠償請求(治療費、休業損害、慰謝料等)、後遺障害等級認定、弁護士費用補償特約等
借金・債務整理
借金の返済でお困りの場合、問題を解決するための債務整理には、自己破産、任意整理、個人再生などの方法があります。弁護士にご依頼いただければ、これまでの支払い状況や現時点での支払い能力、ご依頼者様のご希望を踏まえて、最適な債務整理の方法をご提案いたします。
対応内容
自己破産、任意整理、時効援用、過払い金請求、民事再生、個人再生等
相続・遺言
遺言書が残されていない場合、相続財産の分割について相続人全員で話し合います。しかし、親族間での話し合いは揉めてしまい、トラブルになるケースも少なくありません。弁護士を介することで、的確なアドバイスを受けることができ、遺産分割協議をスムーズに進めることが可能になります。
対応内容
遺産分割協議、遺留分侵害額請求、遺言書作成、遺言執行、相続放棄、成年後見等
離婚・男女問題
離婚をする際には、まずは当事者同士で話し合いをしますが、お互いに感情的になって話し合いが進まず、揉めてしまうことも多くあります。第三者である弁護士を介することで、慰謝料や財産分与、親権、養育費、面会交流などについて、冷静に話し合いを進めていくことができます。
対応内容
離婚、財産分与、親権、養育費、面会交流、慰謝料請求(不貞行為、DV等)
労働問題・労働災害
残業代の未払い、不当解雇、パワハラ・セクハラ、労働災害など、労働関係のトラブルはさまざまなものがあります。会社は労働者にとって働きやすい環境をつくる義務があり、これを怠ると安全配慮義務違反を問われることになります。トラブルが発生した際は、すぐに弁護士にご相談ください。
対応内容
未払い残業代、不当解雇、労働災害、パワハラ・セクハラ、損害賠償、安全配慮義務違反
消費者被害
マルチ商法や投資詐欺、架空請求、出会い系詐欺、リスクの高い金融商品など、最近の詐欺や消費者被害は巧妙化し、早期に対処しないと被害回復が困難になる場合も増えています。しかし、一般の方が一人で解決することは困難です。思わぬトラブルに巻き込まれた方は、弁護士にご相談ください。
対応内容
投資詐欺、架空請求、訪問販売、定期購入に関するトラブル、クーリングオフ
会社・法人のお客様
会社を経営する上で重要になるのが、取引先と交わす契約書で、トラブルを未然に防ぐ役割があります。弁護士が契約書を作成・チェックする際は、契約の内容がすべて網羅されているか、自社に不利な事項がないか、法的に問題はないか、契約書としての形式が整っているかを確認します。
対応内容
契約書作成・チェック、クレーム対応、顧問契約、運営サポート
借地・借家・農地
不動産に関する問題は、賃料増減額や明渡しなど賃貸借でのトラブル、欠陥住宅や土地・建物の売買トラブル、昔の登記が残ったままになっているなど多岐にわたります。不動産についてのトラブルは、専門知識とノウハウが必要になるため、弁護士に相談することをおすすめいたします。
対応内容
契約不適合責任、賃料の増減、賃料未払い、原状回復、明渡し、境界トラブル、登記関係訴訟
刑事事件・少年事件
刑事事件で逮捕された場合、すぐに弁護士に依頼すると、早い段階で弁護活動をスタートすることができ、早期釈放の可能性が高まります。少年事件では、少年がいかに更生できるかを示すことが重要になります。弁護士は法的な弁護活動はもちろん、少年が更生できるように全力でサポートします。
対応内容
逮捕、拘留、起訴、公判請求、略式起訴、不起訴処分、処分保留、実刑判決、執行猶予付き判決等
債権回収
取引先からの売掛金などの回収が滞ると、会社の存続に関わる事態になりかねません。債権回収は迅速な対応が何よりも重要です。相手方に催促の電話をしても支払いがない場合でも、弁護士が電話で交渉したり、弁護士名で内容証明郵便で督促すると、スムーズに回収できる可能性が高くなります。
対応内容
売掛金の回収、内容証明郵便、民事調停、支払督促、仮差押え、訴訟、強制執行
学校・PL・医療事故
学校事故や医療事故、製造物の欠陥などで被害に遭われた場合、まずは事実関係・法的責任の有無に関する調査を行います。弁護士にご依頼いただくと、被害者の方に代わって、相手方や保険会社に損害賠償を請求します。示談交渉がまとまらない場合は、調停や訴訟を提起して解決を目指します。
対応内容
損害賠償請求、災害共済給付制度、後遺症慰謝料請求、治療費請求、医療過誤
その他案件
友人に貸したお金が返ってこない場合は、貸金返還請求をします。暴行・窃盗・横領・詐欺などの被害にあった場合は、相手に対して損害賠償請求を行います。また、インターネット上で誹謗中傷の被害を受けた際は、削除請求、発信者情報開示請求、損害賠償請求、刑事告訴などの対応があります。
鈴木泉法律事務所の特徴
弁護士に相談することは、ハードルが高いと感じる方が多いのではないでしょうか。
当事務所は、地域の皆様が気楽に相談してみようと思える「市民開放型の法律事務所」です。
市民の皆様のよき相談相手になること、市民の皆様の悩み事の解決にお役に立てる存在であり続けることを目指しています。
お気軽にご相談いただけるよう、債務整理、相続、交通事故、離婚の初回相談は無料です。
当事務所には、女性弁護士が在籍しておりますので、ご希望の方はお申し付けください。
また、当事務所には複数の弁護士が在籍しておりますので、困難な事案については、複数の弁護士で対応することも可能です。
ご相談はプライバシーに配慮して、完全個室で行われるので安心してお話しいただけます。
また、お子様と一緒にいらっしゃる方もご相談が可能です。
事務所には駐車場がございますので、お車でお越しの方はぜひご利用ください。